日系社会のフロンティアを尋ねる vol.13 - 夘木健士郎 SUN NOODLE NJ支店ゼネラルマネージャー
日系社会で活躍するリーダーと各界で活躍する日系リーダーを尋ねるシリーズ。第13回目は、SUN NOODLE NJ支店ゼネラル マネージャーの夘木健士郎氏にインタビューした。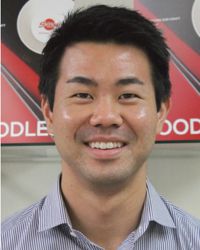
ハワイ生まれ。日系新二世。日本政府が推進する「Cool Japan」のヨーロッパでのイベントに日本企業とともに参加し、本格的なラーメン普及に力を入れている。島本敬三シェフが発案したラーメンバーガーも陰からサポート。SUN NOODLEは栃木県の製麺会社の長男だった父親、栄人氏がハワイに渡り創設。現在は世界中にラーメンの麺を供給し、世界のラーメンブームを支えている。
現在のこだわりは麺のテキスチャー
—世界中で日本食がブームとなって久しいですが、その中でも最近はラーメンがブームで、アメリカでも多くのラーメン店が開店しています。ラーメンはとても奥が深くて繊細なラーメン職人の“こだわりの一杯”ですが、アメリカやヨーロッパでは、どこまでラーメンが浸透しているのでしょうか。
以前、お客様はスープにこだわっていたのですが、現在では麺の食感、私の父がいうには“麺のテキスチャー”を意識して、みなさん、ラーメンを召し上がっています。細麺とか太麺ということではなくて、食感に繊細になっています。
例えば、日本でしたら九州は豚骨で細麺を食べて育ち、札幌でしたら味噌ラーメンの太麺で育ち、好みは地域でおおよそ区分できますが、アメリカやヨーロッパでは、太麺、細麺、縮れ麺など個人によって好みが違います。私と姉はハワイで生まれ育ちました。私はずっと味噌ラーメンを食べていたので縮れの太麺が好きですが、姉は細麺の縮れ麺の醤油ラーメンが好きです。
—ラーメンも、そこまでこだわりを持って日本以外の国で受け入れられているんですね。
日本食が流行り、今は日本食をもっと勉強したいというシェフたちが、京都へ行って日本食を勉強しています。このムーブメントの中にラーメンが入っていて、アメリカ人シェフのアイバン・オーキン氏がアイバン・ラーメンを日本で2軒オープンしました。彼は、アメリカ人がラーメンの世界へ入る道を作りました。
約10年前、アメリカ人シェフのデビッド・チェン氏が、アメリカ人にヌードルバーというコンセプトを紹介して、ラーメンブームに火をつけました。彼は、もっとクールにラーメンを食べれるような雰囲気を作りました。2004年にラーメンブームが巻き起こり、それまでは日本人がアメリカに来てラーメン屋を開いたのが、この頃を境に中華系や韓国系のアメリカ人がラーメンを作り始めました。2008年に一風堂さんがアメリカ進出をして豚骨が流行になりました。
—アメリカ人シェフはラーメンのどの部分に興味を持っているのでしょうか。
スープですね。例えば、フレンチのシェフがコンソメスープを作ると、油を取り除くので、とてもライトになります。ラーメンとは違いますね。だから、フレンチのシェフにとって、ラーメンは未知の世界なんです。もっと学びたいっていう感じです。
以前、カリフォルニア州ナッパのワイナリーと働く機会がありました。そこに日本人のフレンチシェフで元ちゃぶ屋オーナーの森住康二氏がいました。彼が作ったスープのフレイバーはシャープでニートなんです。ナイスで詳細。私のイメージですが、フレンチレストランはクリーンで、ラーメン屋はちょっと汚れているという感じだったんですが、森住氏ののラーメンは、目からうろこでした。ラーメンが違ったレベルな感じでした。想像を使えば、どんなラーメンでも作れるんですよね。
 RAMEN LABで出される醤油ラーメン
RAMEN LABで出される醤油ラーメンRAMEN LABから発信する
—食べ物は人と人との関係を良くしてコミュニケーションを円滑にする役割もあります。夘木さんは、食を通してどんな外交をしたいとお考えですか。
私は少しですが日本語が話せます。多くの日本のシェフがアメリカに進出したいと思っています。しかし言葉が分からない、食材は違う、法律も違う、不動産も違う。怖さもあります。そこで弊社は、アメリカへの進出をしたいという方をヘルプしています。イベントを一緒にやったり、RAMEN LABで2、3日間ポップアップをしたり、食材を試したり、私は必要に応じて通訳や翻訳をしたり、彼らが快適に仕事ができるようにお手伝いをしています。
一方で、アメリカ人のシェフたちは、もっとラーメンのことを知りたがっています。ここで障害になるのが言葉の壁です。アメリカ人シェフは日本語を話さないですし、日本からのシェフは英語を話しません。そこで、私たちが彼らの間に入ります。コミュニケーションがとれることで、食材や素晴らしいアイディアがでて、素晴らしいラーメンができます。私たちは、どうすれば彼らが一緒に仕事をできるかを考え、手伝います。このように、SUN NOODLE社は製麺がメインですが、日米関係をより親密にすることに貢献しています。
—マンハッタンにオープンしたRAMEN LABについて教えてください。
 RAMEN LABのインテリア。10席の客席があり、隣客との距離もなかなかタイト。日本のラーメン屋を彷彿させる
RAMEN LABのインテリア。10席の客席があり、隣客との距離もなかなかタイト。日本のラーメン屋を彷彿させる—RAMEN LABの始まりはどんな感じでしたか。
私がSUN NOODLEに入社して2年半は麺作りをしました。それから営業に出て3年前にニュージャージー(NJ)に引っ越して、2年前にNJに工場ができました。その頃、日本人ではない方たちがラーメンに興味を持っていることが分かり、さらに営業を続けることで、教育が必要だと分かりました。
NJの工場にはテイスティング用のキッチンがあり、そこには小さいカウンターもありました。2013年に私は、Ramen Flight(ラーメン・フライト)に、アメリカ人のラーメンシェフ、チェン氏、ダニエル・ハーゲット氏、オーキン氏らをそれぞれ招待しました。「中村屋」の中村さんが調理した醤油ラーメン(鶏ガラスープと縮れ麺)、豚骨ラーメン、味噌ラーメン、混ぜ麺、つけ麺の5種類を少量ずつ召し上がっていただきました。招待したラーメンシェフたちからは好評を得て、みなさんが「学びたい」と言ってくれました。
そこで今度は一般の方にもやろうとなり、弊社ウェブサイトで毎週月曜日の午前10時に金曜日のイベントを告知しました。人数はペアで、合計6人限定でした。当初、たくさんの方たちが予約をとろうとして、ウェブサイトがクラッシュしてしまいました。その後、NY Timesに取材されました。そのうちに行列ができて、みなさん、ラーメンについて学びたい、技術を学びたいんだと分かったので、マンハッタンでやろうとなったのが、RAMEN LABです。
まさに食文化の“ラーメン大使”ですね。
SUN NOODLEのミッションがそうですからね。ラーメンだけでなく、麺、食における日本人の精神、ルーツを伝えます。
RAMEN LABは小さくて10席だけです。とてもタイトな空間です。昔はラーメンができあがると、お客さんはその一杯に集中して食べました。カウンターの向こうではシェフが調理をしている。見て、料理して、集中する。これが、RAMEN LABのゴールのようなものですね。一般のお客様には、シェフと会話したり、出された一杯のラーメンに集中していただきたいです。
アメリカでも地方色をもったラーメン創造
—夘木さんの描く“本格的ラーメン”像とは、どんなラーメンですか?
ラーメンはとても地元に根ざした食べ物です。豚骨は九州、札幌は味噌という具合にです。さまざまなラーメンが発展した理由は、地元のものを材料に使うからです。僕にとって本当のラーメンというのは、地元の食材を使ったものです。
ラーメンにはフォーカスしている5つの鍵があります。�麺 �スープ。スープは3つに分かれます。�-1、スープの元(ポーク、鶏、魚など)�-2、たれ(醤油だれ、味噌たれ、塩たれ)�-3香と油。ある醤油ラーメンは、鶏油(チーユ)が使われます。�トッピング(チャーシューなど)。
しかし、これらの5つの鍵がなくても、地元の食材でラーメンを作れます。地元にこだわっていることがラーメンで一番大切だと思います。 フードムーブメントがヨーロッパでもアメリカでもあります。特にアメリカでは、地元のものを使うのが流行ってます。食べ物というのは、近くで作られたものほど、より美味しいんです。私がテネシーにいた頃、紫蘇やメンマがとれました。フレッシュなので、日本や中国から輸入するより美味しいです。食のムーブメントでは、地元の食材にこだわります。地元の農家をサポートします。
私の父は19歳でハワイへ渡り、ラーメンの麺作りに励みました。コストが3倍もかかる日本からの小麦粉を使えばレストランに卸せません。そこで、地元の食材を使うしかありませんでした。そして驚くほどの麺を作りました。
 (右から)夘木健士郎SUN NOODLE NJゼネラルマネージャー、父親でSUN NOODLE創設者である栄人SUN NOODLE社長、澤川啓介SUN NOODLE副社長
(右から)夘木健士郎SUN NOODLE NJゼネラルマネージャー、父親でSUN NOODLE創設者である栄人SUN NOODLE社長、澤川啓介SUN NOODLE副社長—日本からアメリカへ進出してきたら、日本と同じ食材が使えるとは限りませんよね。しかし、地元の食材を使うことは、妥協ではありませんよね。
お金をたくさんかけるなら別ですが、ビジネスは無料ではないので、日本と同じコストで同じものを作るのは不可能です。シェフたちは才能があり、地元の食材を尊敬していて、日米の違いを理解しています。しかし、「麺も違うけれど最善を尽くして美味しいラーメンを作ろう」と、不平不満を言わずにラーメン作りをするシェフは、少人数です。
—日米の食材、水、環境の違いに適応できないシェフには、どんなアプローチをしていますか。
シェフに自分自身のスープを作ってもらうと、「アメリカで日本と同じスープを作るのは難しいんだな」と彼らはすぐに分かり、そこからオープンになります。一般のお客様も同様です。東京に行き、ラーメンを召し上がって、アメリカに戻って来て、美味しくないと言います。だからこそ教育が必要です。
—ラーメンシェフはアーティストで職人でもあるから大変ですね。
 NYのRAMEN LABでラーメンを差し出す中村栄利シェフ。「お兄さんのような人。RAMEN LABは、中村シェフなしではあり得ないことです」と夘木氏
NYのRAMEN LABでラーメンを差し出す中村栄利シェフ。「お兄さんのような人。RAMEN LABは、中村シェフなしではあり得ないことです」と夘木氏将来は、札幌ラーメン、東京ラーメン、博多ラーメンは、ニューヨークラーメン、ロサンゼルスラーメン、ハワイラーメンみたいな感じに地方色をもたせます。この方向性ならラーメンは広がり続けるでしょう。
写真・文・構成 Tomomi Kanemaru
2015/01/31 掲載











