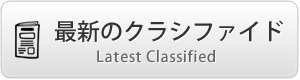マイ・ワード・マイ・ヴォイス
vol.67 灰色の鳥(2)
2026-01-04
「どう生きるか」と「どう死ぬか」を同じものと捉えた哲学者がプラトンです。彼は対話篇『パイドン』で、死刑を直前に控えたソクラテスが「哲学とは死の練習である」から死を恐れることはない、と語る姿を描いています。「哲学とは死の練習である」とは一体、どういう意味でしょうか?これは「生きることは即ち死に向かうことである」とか「生きることは死んでないことだ」とか「人は死ぬまで生きてる」といった、意味のない同語反復ではありません。
プラトンは「哲学は魂を肉体の関与から解放する行為である」と主張します。哲学が探求する知恵とは感情ではなく思考によってのみ得られるものであり、肉体の関与、つまり飲食や衣装や装飾品などによる感情や感覚への影響は探求の役に立たないどころか障害物であって、哲学者はそれらから自由になる努力をすべきである。死とは魂と肉体を分離する機会だから喜ばしいものであり、逆に、生きるとは魂と肉体との分離の予行練習にすぎないのである、と。
現代人からするとかなり極端な考え方ではないでしょうか。自己啓発本やセミナーなどを利用して多くの人が「どうすれば自分にとって楽しい人生を送れるか」を求め、そこまではしないとしても、自分の夢が実現すること、確固たる経済的基盤を得ること、衣食住が満たされること、家族や人間関係に恵まれること、愛情や友情により心理的に充実することなどが「幸せな人生」の条件と捉える人が多いのが現代ではないでしょうか。プラトンからすると、それらは全て「嬉しい」「楽しい」といった感情や感覚に訴えることであり、理性による知恵の探求には役立たない。それどころか、探求の障害物でしかないというのです。要するに、プラトンの描く最高の人生とは「幸せ」とは関係ないのです。「楽しい」「嬉しい」という感覚から解放されて真理を知ること、知恵を得ることが人生の目的なのです。
「なんだ、プラトンってすごい哲学者だと思っていたけど、そんな極端な人だったのか。がっかり。現実が全く見えてない人だったんだな」と思われた読者もいるでしょうか。彼がなぜこのように考えたのか、そのロジックをたどってみましょう。(続く)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。
哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。