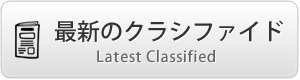マイ・ワード・マイ・ヴォイス
Vol.15 粗忽者
2021-09-03
落語に『粗忽長屋(そこつながや)』という噺があります。粗忽(うっかり)者の八五郎が歩いていると黒山の人だかりが。身元の分からない行き倒れだという。その死体の顔を見た八五郎は「これは俺の弟分の熊五郎だ!」と驚く。独り身で親戚もいない熊五郎の身元を確認するには「本人をここに連れてくるのが一番だ」と言い出し、急いで熊五郎の家に。家にいる熊五郎に「お前は死んだぞ」「死んだ気がしないかもしれないが、最初はみんなそんなもんだ」「お前の兄貴分の俺が言うんだから間違いない」と言い、これまた粗忽者の熊五郎を現場に連れてくる。「自分の死体」を抱いて泣き崩れる熊五郎。最後に一言「でもなんだか分からなくなってきたぞ。抱かれているのは確かに俺だが、抱いているこの俺は一体誰だろう」。
2人の粗忽者が赤の他人の死体を熊五郎と信じ込む間抜けさ、その間抜けさが度を越している様子を笑う噺なのですが、立川談志はこれに独自な解釈を加えて伝説を残しています。他の落語家たちのバージョンでは八五郎が単に「現実を認識できない、論理的思考のできない間抜け」と描かれていますが、談志の八五郎は熱情とエネルギーに溢れた男として登場します。自分の思い込みに疑問を抱かないどころか、熊五郎に対して「お前は死んだ」と凄まじい勢いで畳み掛け、本人を「死んだ」と納得させてしまう。談志によるその畳み掛けが秀逸で、巧みな言葉遣いと勢いが見ている私たちを一瞬だけ「これは自分が死んだことに気づかずに自分を抱く男を描いたファンタジーかもしれない」と思わせるほど。八五郎の主観的世界観(思い込み)が溢れ出し、熊五郎や周りの人の客観的世界観(事実)を飲み込み、ついには『粗忽長屋』という噺の客観性をも曖昧にさせてしまう。談志は自らのバージョンを「主観長屋」と呼んでいました。
熱情をもって繰り返される陰謀論が「世界の客観的事実」を曖昧にする現代に通じる噺ではないでしょうか。デジタルメディアから溢れ出る情報の濁流に晒された私たちは、常に八五郎になる可能性と隣り合わせで生きています。そんな世界の中で「粗忽長屋」を笑う瞬間を大切にしたいと思うのは私だけでしょうか。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。
哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。