あんな家こんな人
vol.16 忍者参上
2018-10-18
【志能便】
「忍者」「忍びの者」は、昭和になって小説家が作り出した言葉で、明治大正期は、「忍術遣い」と呼ばれていたそうです。実は、聖徳太子の頃から使われていたのが、「志能便しのび」もしくは「志能備しのび」。そのため、後世、「細人」、「細作」と書いて“シノビ”と読むようになったと言われます。
【仕事】
最も活躍したのが、戦国時代。国取りに明け暮れ、戦国大名が、合戦を有利にするため、他国の情報を得るのに、忍者を雇い、諜報活動につかったようです。忍術研究家の奥平兵七郎氏も「主人によき便り、牒報をもたらすべく志す者の意」と解釈しています。
【忍者と風水】
アニメやゲームで「火遁 ◯◯の術」「水遁 ◯◯法」と忍者が叫んで攻撃しているシーンを見かけます。実際に、忍者の兵書に『五遁ごとん』というのがあり、『木火土金水』を使って、「遁げる」つまり「逃げる、逃れる」ことを記しています。自然現象や心理学、科学を応用した隠れ身の術の一種で、忍者の本質でもあり重要な術と云われています。気になったのは、『木火土金水』は、東洋五術の基本であり、我々風水師にとって、『木火土金水』無くして、占術はあり得ないからです。
【占い】
三国志で有名な諸葛亮孔明が使った兵法「奇門遁甲きもんとんこう」は、忍術の源流の兵書のひとつです。遁法の名の由来と考えられていますが、ナント我々、風水師もこの『奇門遁甲』を中国占術の1つとして、行なっております。
【ルーツ】
忍者の術の1つに『七方出ななほうで』という変装があります。出家僧や山伏から旅芸人や商人に変装し、諜報活動を行なったと云われます。香りもそれらしく見せる重要な要素で、線香の匂いのしない出家は怪しく、護摩ごまの匂いは山伏、呉服屋ならキャラの香りなど、和薬の知識も必要だった訳です。そして、実際の表の職業は、農業や商人として生活していたといいます。薬問屋も多く居たといいます。薬の行商人となり、全国を行脚したそうです。そして、小椋かよこのルーツも三重県の薬問屋、つまり『甲賀近くの薬問屋=甲賀忍者』と親戚内では云われています。ご先祖様が行なっていた奇門遁甲も年内には、成就したいと願う平成の風水師でありまする。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

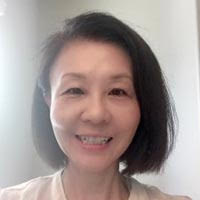 全米発日系風水店DRAGONGOD風水師、黒門アカデミー認定講師。’09年NY・NJ州に開業。東京タワー、マザー牧場始め、経営者、医療関係、飲食店、IT企業、米有名ロックバンド、ハリウッド映画等。CA、NY、ハワイ、日本に顧客。
全米発日系風水店DRAGONGOD風水師、黒門アカデミー認定講師。’09年NY・NJ州に開業。東京タワー、マザー牧場始め、経営者、医療関係、飲食店、IT企業、米有名ロックバンド、ハリウッド映画等。CA、NY、ハワイ、日本に顧客。








