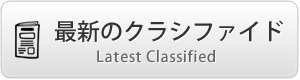苦楽歳時記
第222回 ポエトリー
2016-10-27
一九九七年の早春に初めてパリヘ赴いた。朝から夜遅くまで仕事に拘束された出張であったが、一日だけの非番を利用して、僕はモンパルナス墓地に埋葬されているボード・レールの墓に、真っ先に詣でたのである。
昼前になって小雨が降りだしたが、知人がホテルまで車で迎えに来てくれたので、ミラボー橋まで案内してもらった。かねてからパリヘ行く機会があったら、この橋の上に立って、ギィヨーム・アポリネールの詩『ミラボー橋』を朗読しようと決めていたのだ。あいにくパリの空は灰色の影を落としていたが、念願が叶った僕は気分が晴れて欣快となっていた。
以来、度々パリの街を訪れるようになった。ボード・レールが『悪の華』を執筆したセーヌ河畔のホテルで『現代フランス詩論』を読み、モンマルトルの丘のホテルでは、トリスタン・ツァラの詩集を読みあさり、モンパルナスのカフェではアンリ・ミショーの詩についてペンを走らせた。
ビクトル・ユーゴやマラメル、ヴァレリーにランボー、そしてジャン・コクトーらの詩人の偉業が、今でもパリの街角に色濃く漂っている。これほど詩人の香りに満ちあふれている繁華な街路は、世界中どこを歩いてもたどり着かないだろう。
さて、詩は英語でポエム(poem)とポエトリー(poetry)に分かれる。前者は個々の詩作品である概念(固体概念・単独概念)を指し、後者は詩の本質である概念の内包である。
日本語には「詩」という単一的な言葉しかない。従ってポエムとポエトリーを同義的に捉えてしまう傾向がある。ポエムは「詩」と訳していただいて差し支えはないのだが、明治の初めに外山正一らの提言で始まった『新体詩』を、ポエトリーと正式に訳すことによって、自由詩の抽象性を定義付けすることは出来なかったのだろうかと、考える。
明治十五年に出版された『新体詩抄』の序文には、以下のように謳われている。「この書に載する所は詩にあらず、歌にあらず、しかも之を詩というは泰西のポエトリーという語、即ち歌と詩を総称する名にあるのみ。古よりのいわゆる詩にあらざるなり」
僕はポエム「詩」に対して、ポエトリーを「新体詩」あるいは「現代詩」、「自由詩」と解するように心掛けている。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。