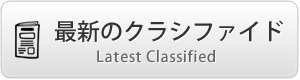苦楽歳時記
第220回 釣り宿の女将
2016-10-13
かつて、日本の知り合が新しい乳化済を開発したので、プロモーション・ビデオを制作してほしいとの連絡があった。
ハイクオリティーで、アメリカのプロの業者に請け負っていただきたいと言う。最後に、金に糸目はつけないと結んだ。
早速、NHKロサンゼルス顧問と相談したら、ドラフトを作製しろと言われたので、時間の調整をおこないCBSの撮影クルーたちと日本へ向かった。ディレクターの要望で、撮影のために関西から東海地方を巡った。
ある日、雨が降り出したので、その日の撮影を打ち切りにした。海のそばにある、小高い丘の斜面に建つひなびた釣り宿に駆け込んだ。
撮影クルーたちは、リモデルされた部屋をあてがわれた。僕は母屋二階の端にある、いかにも古めかしい昭和初期を彷彿とさせる部屋。魚か油のような臭いがしたので窓を開けると、眼下には墓地がくすぶって見えた。
蒲団の上に身体を横にしてうとうとしていると、廊下のきしむ音がする。音は部屋の前で止まった。障子が開いた。釣り宿の女将が立っていた。
「お変わりございませんか。墓地のとなりに小さな火葬場がありまして、あいにく雨なので煙はたなびきません。また来ます」。
余計なことを夜中に告げることか、また来る? どういうことであろうか。
明け方に、寝返りを打って気がついた。女将が横に寝ている。僕は狼狽した猫のように、飛び跳ねて蒲団から逃れた。
「お客さんの匂い良い香りがする」。そう言って、薄気味悪い目つきで近づいてくる。僕は障子を打ち開いてトイレの中に飛び込んだ。
その夜、釣り宿の主人と話をした。彼は面目なさそうに、「家内は統合失調症で、お客様が朝出かけられた直後に、精神病院の職員の方がこられまして再入院させました」。
彼は虚しさを耐えるように肩を落として、なえた顔でそう語った。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。