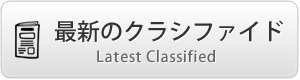苦楽歳時記
第218回 スティーブと川端康成
2016-09-29
つい最近、パサデナのオールドタウンで、懐かしい旧知と邂逅(かいこう)した。そこには背の高い痩身の男性が佇んでいた。風貌は往時のままだったので、三十三年ほど前に日米文化会館において、日本語を教えたことのあるスティーブだと、ひと目見てわかった。
当時の彼の日本語はたどたどしかったが、日本文学に対する造詣が極めて深かった。「国境の長いトンネルを抜けると、雪国であった… 」。
「美しく、素晴らしい書き出しですね」。スティーブは、川端康成の『雪国』の冒頭をしきりに称えていた。
このわずかな文章の真相をとらえるということは、俳諧に通じる感性がすくよかでなければならない。僕はスティーブに定型詩について尋ねると、彼は得意になって芭蕉や蕪村の句をそらんじてみせた。
川端康成の文章が巧緻である所以は、『雪国』の冒頭に関して論じるならば、明瞭簡潔にしてその状況が読者の心をとらえ、想像力が風花(かざはな)のように変化をとげていくようだ。
「国境の長いトンネルを抜けると、雪国であった」。そして、この後に「夜の底が白くなった」と短いセンテンスが続くのだが、この小さな一行は、「信号所に汽車が止まった」となって、最初の段落を結んでいる。
いわば、短文と書き出しの短文をつなぐ、散文詩的要素と俳諧至情に准ずる創作の技法が、混交した幻想的な状況描写となっている。この手法は伊藤 整の言葉を借用するならば、「美の頂上を注出する現象から省略」である。
往日の僕はスティーブに話しを続けた。川端が『雪国』を脱稿した折りに、「国境の長いトンネルを… 」の前に、四百字詰め原稿用紙三枚ほどの文章が綴られていた。川端自身が削ったのか、編集者に指摘されて改稿したのかは謎である。
久々に出くわしたスティーブは、随分と日本語が流暢になっているので驚いた。三十年ほど前に、同志社大学大学院へ留学したという。互いのメールアドレスを交換して別れる間際に、「苦楽歳時記、読んでいます」。
スティーブは相好を崩して雑踏の中に消えてしまった。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。