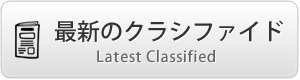苦楽歳時記
第212回 オニール夫妻
2016-08-18
学生の頃、ビバリーヒルズの屋敷に居候をしていたときに、オニール夫妻が深夜になって帰宅した。ミスターはボウタイゆるめながら、ソファーの上にのけ反りかえってブツブツと呟きはじめた。かなり酩酊している様子であった。
僕は名前を呼ばれたので、リビングルームへと向かった。「何が、マイウエイだ。三日間も待たせやがって」と、吐き捨てるように口走っている。
だいぶ荒れている様子だったので、僕はおそるおそるミスターに話しかけてみた。泥酔していて、ろれつが怪しいから解りづらいところがあったが、よくよく話を聞いてみると、フランク・シナトラは時間にルーズな奴だという。
ミスター・フィリップ・オニールは、元ハリウッド映画の制作に従事していた者だ。
事の起こりはこうだ。ある映画の撮影の際に、何十人もの撮影クルーが三日間待ちぼうけをくらっていた。そのころからスターであったフランク・シナトラが、悪ぶれたそぶり一つ見せずに、ロケ地に現れたのである。
あのころから、フランク・シナトラは横着者で通っていたらしく、ミスターは、三十五年前のことを未だに根に持っているらしい。
オニール邸の斜め向かいには、ジャズシンガーのエラフィツ・ジェラルド邸があり、更に数百メートル上ったところに、ロバート・ワーグナー邸がある。フランク・シナトラ邸は、車で十分ほどの所にある大邸宅だ。
ミセスのジャネット・オニール(当時六十五歳)は、はんなりとした優しい夫人で、僕はアメリカの母として慕っていた。
夕刻に、ミセスが作る料理の助手を務めながら、週に一度、一時間くらい掃除をした。必ず、第一土曜日のティータイムの際に、ミセスから毎月五〇ドルの小遣いを頂戴した。
僕の書斎の壁に掛けてあるミセス・ジャネット・オニールの若かりし似顔絵が、きょうも麗しげにほほ笑みを投じている。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。