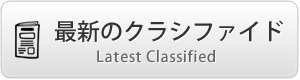苦楽歳時記
vol164 絶望
2015-09-10
最近、生命(いのち)のことについて考えることがある。困難な手術を幾度も行い、手厚い看護と治療を施されて、クリニカル・トライアル・メディスン(抗癌剤)を服用して今まで生きながらえてきた。それ自体には感謝してもしきれないほどだ。
しかし、右半身麻痺で身体の自由が奪われてからは、一日中、家の中で過ごしていると、突として焦燥感に襲われてしまう。
僕は日頃から旅にでるのが好きであるから、そんなときには異郷に草枕する夢を描いて、自らを慰めることしかできないのである。
何のために生きているのかとしばし考える。どこに行くにしても介護が必要だから、家族に迷惑ばかりかけているのではないかと、つと深く悩んでしまう。独りきりでのべつ家の中にいると、否定的な想いが脳裏をかけめぐる。
便々たる後半生を歩んでいると何もかもが嫌になる。けれども、書斎の壁に貼りつけてある格言を見る度に心に灯がともる。
「生きることへの絶望なくして、生きることへの愛はない」(アルベール・カミュ『裏と表』より)
どのような人間にも闘いがある。相剋(そうこく)がある。患難が襲いかかってくる。そう考えると、僕も人並みだとかえりみて平穏になれるのである。
人間は絶望と隣り合わせで生きている。絶望なくしてまことの人生は歩めない。絶望なくして「愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制」は示せない。
そして、絶望を知らなければ真の喜劇戯曲も描けない。絶望は金色(こんじき)に輝く冠だ。
ドイツの作家ヘルマン・ヘッセが、絶望についてこのように述べている。「神が我々に絶望を送るのは、我々を殺すためではなく、我々の中に新しい生命を呼び覚ますためである」。
キェルケゴールがたどりついた「主体的真理」は、「自分は無力だが、そのうえで確固たる信仰に生きる」。
僕の行きつく先はこれであると確信を得た。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。