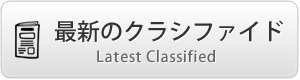苦楽歳時記
vol157 芥川龍之介の死
2015-07-23
僕が文芸講演にデビューしたのは、一九八〇年の新春である。『芥川龍之介/羅生門再考』と題した講演会は、会場で講壇から語る形式ではなく、二百人ほどの聴衆と一緒に洛南(京都)の街を歩きながら、僕は拡声器を持って要所で立ち止まっては解説をした。
芥川龍之介は『或る阿呆の一生』の中で、「人生は一行のボオドレエルにも若(し)かない」と書いている。この一行は往時の僕の心を強く惹きつけていた。芥川自身は英文学を学びながら、フランス文学もこよなく愛していたのである。
芥川の代表作品といえば『鼻』、『羅生門』、『蜘蛛の糸』、『河童』。そして『芋粥』や『歯車』である。そしてこれらの作品は、よく論じられている。だが、クリスチャン作家の遠藤周作と佐古純一郎だけは、『神々の微笑』の重要性を指摘しているのだ。
遠藤はエッセイ『「神々の微笑」の意味』の中で、「神々の微笑」の恐ろしさについて、次のように述べている。
芥川龍之介が老人の口をかりて、いかなる外国の宗教も思想もそこへ移植すればその根が腐り、その実体が消滅し、外形だけはたしかに昔のままだが、実は似而非(えせ)なるものに変わってしまう日本の精神風土を指摘していることだ 。
「あなたは天主教(カトリック)を弘(ひろ)めに来てますね」と老人は言う。「それも悪いことではないかも知りません。しかしデウスもこの国へ来てはきっと最後には負けてしまいますよ」
遠藤は、老人というよりは日本人そのものなのであるという。
芥川は「あらゆる神の属性中、最も神の為に同情するのは、神には自殺を出来ないことである」(『侏儒の言葉』)、「神々は不幸にも我々のように自殺出来ない」(『或る阿呆の一生』)という辛辣(しんらつ)な文言を書き残している。
小松伸六は「『美を見し人は』/自殺作家の系譜」の中で、芥川を神なき日本人の象徴的存在ではなかったかと提起している。
欧米では、自殺は尊厳死(自然死)に反して神にそむく悪とされているが、芥川は「或旧友へ送る手記」(遺稿)に、「僕は紅毛人たちの信じるように、自殺することを罪悪とは思っていない。仏陀は現に阿含経で、彼の弟子の自殺を肯定している」と記している。
聖書にも一言も自殺を禁じた文章は無いので、小松伸六は芥川説を支持している。だが、僭越ながら反論させて頂くと、日本に仏教が伝来以来、仏教はどのような条件の下でも、自殺を容認したという形跡は見当らない。
また、たとえ聖書に自殺を否定する記述がなくとも、聖書が教えている倫理観念は、自殺を否定していることに間違いはない。従って、人間共同体に対する罪だけではなくして、普遍的絶対者である神の御前で、それぞれが罪を認めない限り、自殺の問題を含めて真の解決法は困難を極める。
精神科医の大原健士郎は、芥川の自殺を「自己分析的自殺」と名付けたが、大方の精神科医の見解と同じである。また、芥川には明らかに分裂病態があった。同じく精神科医の梶谷哲男によると、統合失調症(分裂病)の初期は創作に対してプラスの働きを示すそうである。
加賀乙彦は『歯車』の異常性心理は、芥川の実体験に基づくものであると断定しているが、その理由の一つがリアリティである。けれども、作品にあらわれている異常心理は案外単純で、真の狂気というよりは、極度な不安による抑鬱であると診断している。
芥川は枕辺に聖書を置き、睡眠薬で自殺を遂げる寸前まで聖書を読みつづけていた。作家として、読書家として、或いは知識人として最後にたどり着いたのが『聖書』であった。芥川も、まさしくキリストによって救われようとしていたのである。
芥川の自殺は吉本隆明が指摘するように、純然たる文学的な、また文学作品的な死であって、人間的、現実的な死ではなかった。
聖書には旧約の創造文学や終末文学、そして新約におけるキリストのたとえは文学的価値が非常に高い。芥川は「善きサマリ人」と「放蕩息子」(ルカによる福音書)のたとえ話を短編小説の手本であると述べている。だが、聖書を神の言葉として受け入れることなくして、自らの命を絶ってしまった。
最後に、芥川が二十二歳の時に恒藤 恭へ宛てた書簡を紹介する。
「僕はイゴイズムをはなれた愛の存在を疑ふ。僕は時時やりきれないと思ふ事がある。何故、こんなにして迄も生存をつづける必要があるのだろうと思ふ事がある。そして最後に神に対する復讐は、自己の生存を失ふ事だと思ふ事がある。僕はどうすればいいのかわからない」
本日、七月二十四日は、芥川龍之介の祥月命日『河童忌』。
※本文の登場人物の書いたものは、原文のままといたしました。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。