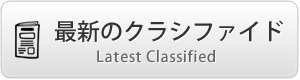苦楽歳時記
vol145 パリとお茶漬け
2015-04-30
一九九七年の早春、クライアントが新しい事業を興すにあたり、僕は加勢に赴くために初めてパリへ向かったのである。まず、シャルル・ドゴール空港より、市街地に向かうリムジンバスを利用した。
バスの車窓から見える景色を眺めているうちに、何だか日本に里帰りしているような錯覚に陥った。建物や植物が、何となく懐かしさを漂わせていたからだ。
モンパルナスのホテルにチェックインしてから、幾人かのフランス人と話す機会を得た。アメリカ人と対比して、身のこなしや雰囲気が随分と違う。同じ西洋人なのに、フランス人の方が日本人に近いように思えた。僕はフランス人に親近感を抱きながら、どことなく、とっつきにくさも感じていた。
ピカソ美術館での鑑賞を終えた帰りに、そこここに大きな落書きがしてあった。僕は足を止めて、たまゆら落書きを見つめた。
ロサンゼルスのフリーウェーなどで見かける落書きとは違って、丸みを帯びた抽象画で構図も色彩も巧みだ。これも芸術の都といわれるゆえんなのであろうか。
夕刻のスタッフ・ミーティングの際に、気落ちさせる出来事が起こった。晩餐に本場のフランス料理を味わえることを幾日も前から鶴首していたのに、たどりついた先は日本人が営む居酒屋だった。クライアントはタテメシしか食さない人だとわかって、がっかりとさせられた。
休日に、現地のコーディネーターがクライアントに水を向けてくれた。クライアントはポンと膝を叩いて、「フランス料理店に、ひとつ行ってみるか」と切り返した。
佳味で豪奢(ごうしゃ)なフランス料理を賞味した後で、クライアントは僕に耳打ちをした。
「デザートに、お茶漬けを食べたいなぁ」
僕はホテルに戻ってから食べるのかと思っていたら、「聞け、聞け」と言う。あまりしつこく言うので、僕はギャルソン(給仕)にお茶を濁してみた。今度は僕が、英語のわからないクライアントに耳打ちをした。
「あいにく、きょうは(お茶漬け)ございませんですって!」
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。