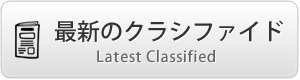苦楽歳時記
vol140 詩とジャズと酒
2015-03-27
中学二年生の秋ごろから、片恋の癒しを求めて数編の詩を味読した。僕は恋多き詩人、ゲーテの詩の数々に魅了されてしまったのである。
高校に進学すると、詩集を片手にジャズ喫茶で過ごすことが多くなっていた。僕の心の内側では、いつも詩とジャズが寄り添い合っていたのである。大学生になってから、もう一つ寄り添うものが増えた。それは、百薬の長の酒だ。
ジャズを聴きながら杯を重ねて、詩集をひもといているときが、この上なく万福のときである。およそ四十年近くも、かたくなにこのスタイルを崩していない。
ジャズを聴くばかりでは物足りなさを感じていた折りに、自動車教習所の講習料をキャンセルして、中古のクラリネットを購入した。一年後に念願叶って、ヤマハの新品のテナーサックスに持ち替えた。
一九年前に、ウエスト・ロサンゼルスの教会で、自作の詩の朗読会を催した。ジャズの生演奏をバックに、自作の詩を自ら朗読したのである。
二十分間のジャズの生演奏が終わった後で、詩の朗読が始まることは聞いていたが、ミュージシャンの面々は、どこか見覚えのある顔ぶれだ。
まさか、と思った瞬間、吾が目を疑った。ステージには、ボブ・フローレンス(ピアノ)、
パット・セネター(ベース)、ビリー・ヒギンズ(ドラム)。一流のミュージシャンがスタンバイしていた。
「ボブ・フローレンスが僕の前座かよう…… 」。僕は相好を崩して小声でつぶやいた。
有名なジャズ・プレーヤーが、日系の小さな教会にふらりと現れて、演奏が終われば何事もなかったかのように微笑みを投じて立ち去った。この時ばかりは、つくづくアメリカだなと思った。
後日、サウザンド・オークスの拙宅の近隣に、ボブ・フローレンスの住まいがあることが判明した。それ以来、ボブとの交流が深まった。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。