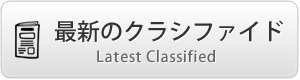苦楽歳時記
vol103 京の都と檸檬(れもん)
2014-07-07
十年ほど前に、急ぎの用で日本へかけつけたことがあった。役目もひと段落したので、友の住まいのある京都まで足をのばしてみることにした。
京都盆地の盛夏は、そよとの風も吹かずにむしむしとしている。僕は莫逆の友が指定した、花見小路のお茶屋『栩栩膳』(くくぜん)ののれんをくぐった。
祇園(ぎおん)界隈のお茶屋は一見さんお断りだ。けれども、時代は変わり不況が長引く中で、一見も受け入れるようになってしまった。そもそも茶屋は、仕出し屋に響膳をお願いしていたのである。
約束の時間よりも早く着きすぎた僕は、鱧(はも)の落としを肴に伏見の冷酒をたしなんでいた。しばらくして隣のテーブルに、艶治(えんや)な容姿の婦女二人が腰を下ろした。そこはかとなくただよう香木の香りに、僕の心根は忘我へといざなわれてしまったのである。
どうやら祇園花街の粋筋らしい。たおやかな若い女性は、山吹色のワンピースをしっぽりと着こなしていた。四十がらみのはんなりとした女は、紗(しゃ)の着物に絽(ろ)の帯をしめて、薄い反物(たんもの)の中に、繊麗な体が人魚のように映えていた。
若い女性にうながされて、女は小ぶりのバッグを開いた。女の顔がうつむいて、美しい白鷺(しらさぎ)の襟足をかいま見た。
やがて友が現れて、旬の料理を味わいながら思い出話しに花が咲いた。茶屋を後にしてからは、先斗町(ぽんとちょう)を歩いて三条に出たところで友と別れた。僕は一人で三条から寺町通りまで歩いた。
若かりし頃、梶井基次郎の珠玉短編『檸檬』(れもん)を味読して、主人公がレモンを買った果物屋を探し求めた。その果物屋らしき店が寺町通りで見つかった。往時、見つけた『八百卯』で、僕は一つ、レモンを手にとった。
七夕(しちせき)の京の街を歩みながら、僕はレモンをガリリとかじった。ほとばしる青春の追憶に、おぼろげな陽炎(かげろう)がいつまでも立ちのぼっていた。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。