Vol.77 こんなとき、どうする?「日本にいる父が自宅から緊急搬送。母は在宅介護で認知症②更なる壁編」
今年に入ってから海外在住の方から日本で暮らしている親御さんの緊急対応のご相談が増えています。前回から3回シリーズで海外在住の方に「どのような壁が訪れるのか」を実例を交えてご紹介しています。2回目となる今回は日本の社会で起こる「コミュニケーションギャップ」についてお伝えします。日本の社会で次々訪れる壁。
その原因のひとつは「コミュニケーションギャップ」。
アメリカで30年以上暮らしているAさん。お母様は認知症で在宅介護。お父様がお母様の介護をされていましたが、お父様が自宅で倒れて緊急搬送されたため、Aさんは日本へ緊急帰国。お父様は倒れてから言葉での意思疎通ができなくなりました。そこで、Aさんはご両親の対応のため、一時帰国中に病院、老人ホーム、銀行や行政などとのやり取りを始めました。Aさんは日本語の読み書きは普通にできますが、各所の窓口へ行って交渉を始めると、どうしても上手くいかない。自分の意思や希望が窓口の担当者に伝わらずストップしてしまう。その原因のひとつには「コミュニケーションギャップ」がありました。30年以上アメリカで暮らしているAさんは、普段英語を使う環境で生活しています。知らず知らずのうちに頭の中が英語の文法や表現方法を使う「英語脳」になっていました。英語は「主語→述語」の文法のため、結論を先に示して、その後に理由を伝えます。そして、自分の意思や希望はハッキリと明確に伝える。日本の社会では(ビジネスシーンでも同じ)、結論は一番最後か、話の途中に紛れ込んでいて、表現もあいまい。直接的でストレートな表現は避ける傾向にあり、どれが結論なのかが分かりにくい。「英語脳」と「日本語脳」を使っていることに気付かずにやり取りすると、お互いに上手く伝えることができなくなります。ここに「コミュニケーションギャップ」が生じます。
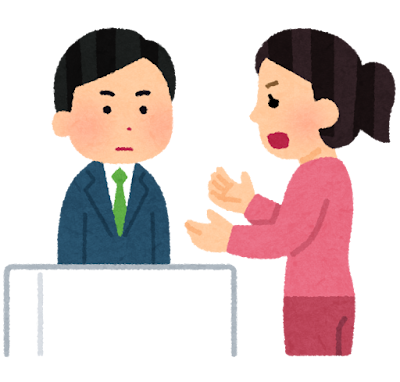
日本の独特な慣習や社会のルールを
踏まえて交渉すれば、スムーズに進む。
世界各国どの国でもそれぞれの慣習や社会のルールがあります。たとえ日本語が理解できていても、日本の慣習や社会のルールに沿って物事を動かしていかないと上手く進みません。ビジネスシーンでの日本語の言葉選びや伝える順序、専門用語など、表現方法も日本独特であるため、Aさんの場合は、行政や銀行、法律関連は専門家である行政書士が代行、医師やソーシャルワーカー、ケアマネジャーなどは専任の介護相談員のアドバイスのもと交渉。するとAさんが交渉していたときには上手くいかなかったことがスムーズに進み始めました。世界ではデジタル化が進んでいますが、日本ではまだまだ紙の書類が必要です。いわゆる「ペーパーワーク」が山ほど存在して、それらに対応しているとかなりの時間を費やします。それも各種書類は普段使わない専門用語ばかり。行政や銀行、法律関連、医療・介護関連は専門家に任せ、ご家族は親御さんとの貴重な時間を大切にされることを私はお勧めします
時代は変わりました。家族だけで介護をする時代は終わりです。
ご家族だけで解決するのは無理です。専門家とチームを組んで前に進んでまいりましょう。私達はあなたの応援団です。バックヤードでいつもあなたを思いっきり応援しています。
日本の介護・実家の処分、相続など各種相談はコチラまで!(初回相談無料)
スペシャリストがあなたのために動くトータルサービス
◆「日本の介護サービスで海外在住日本人を応援するサロンドハース」
[総合窓口:日本]一般社団法人Hearth(ハース)
hearth777@gmail.com
ひとくちメモ ~私の母86歳~ No.76
「母と一緒に老人ホーム見学にいく」の巻②
東京で独り暮らしをしている母。今はまだ一人で生活できているけれど必ず限界が来る。その時はホーム入居してもらいたい娘(私)。そこで母が好みそうなホームを選び見学してみることにした。母にとっては初めての老人ホーム見学。ホームの館内は明るく、大きな窓から庭の緑が見える。訪れたときは、ちょうどお昼時。ご入居者の皆さんがダイニングでお昼ご飯を召し上がっていた。私と母もご入居者と同じメニューを試食して、居室や共有スペースを見学。その日はそのまま母とはホームで別れた。数日後、母の家へ行って見学したホームの印象を聞いてみると…。(続く)










